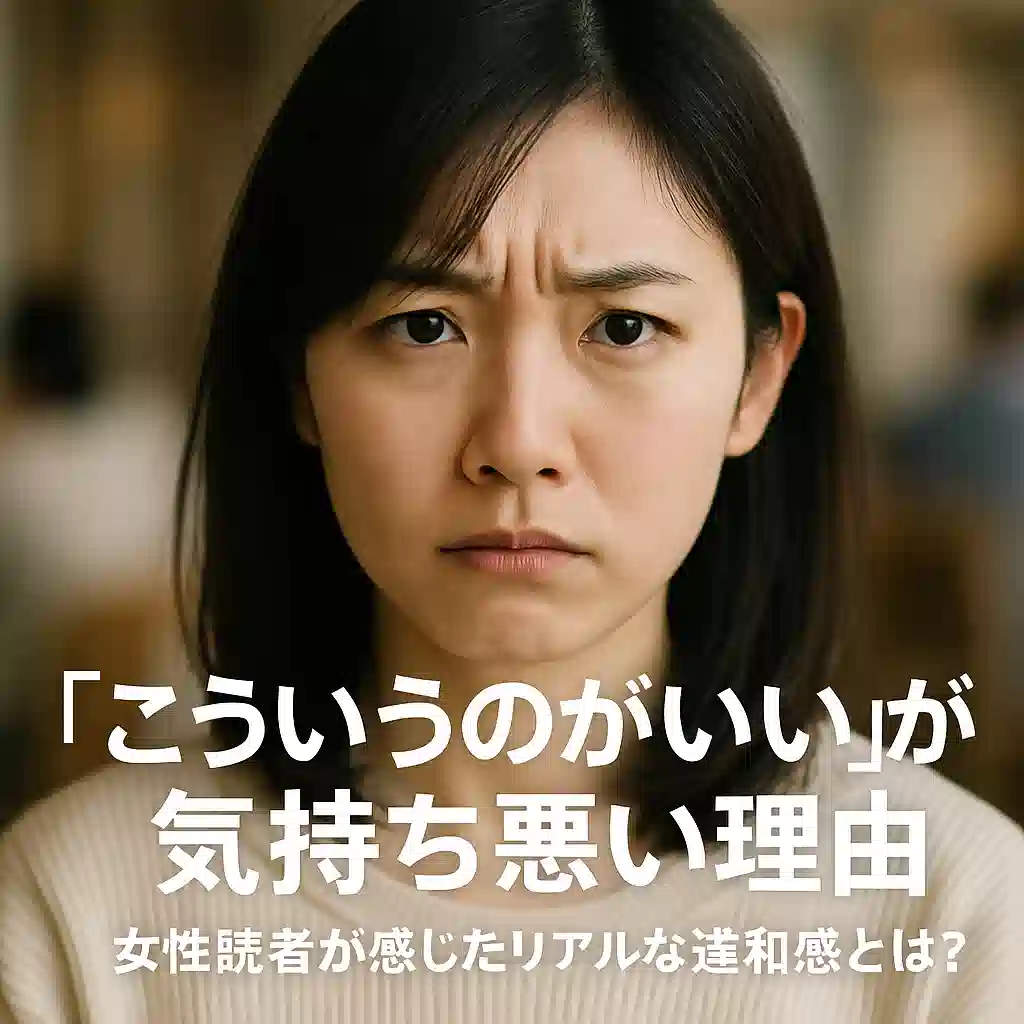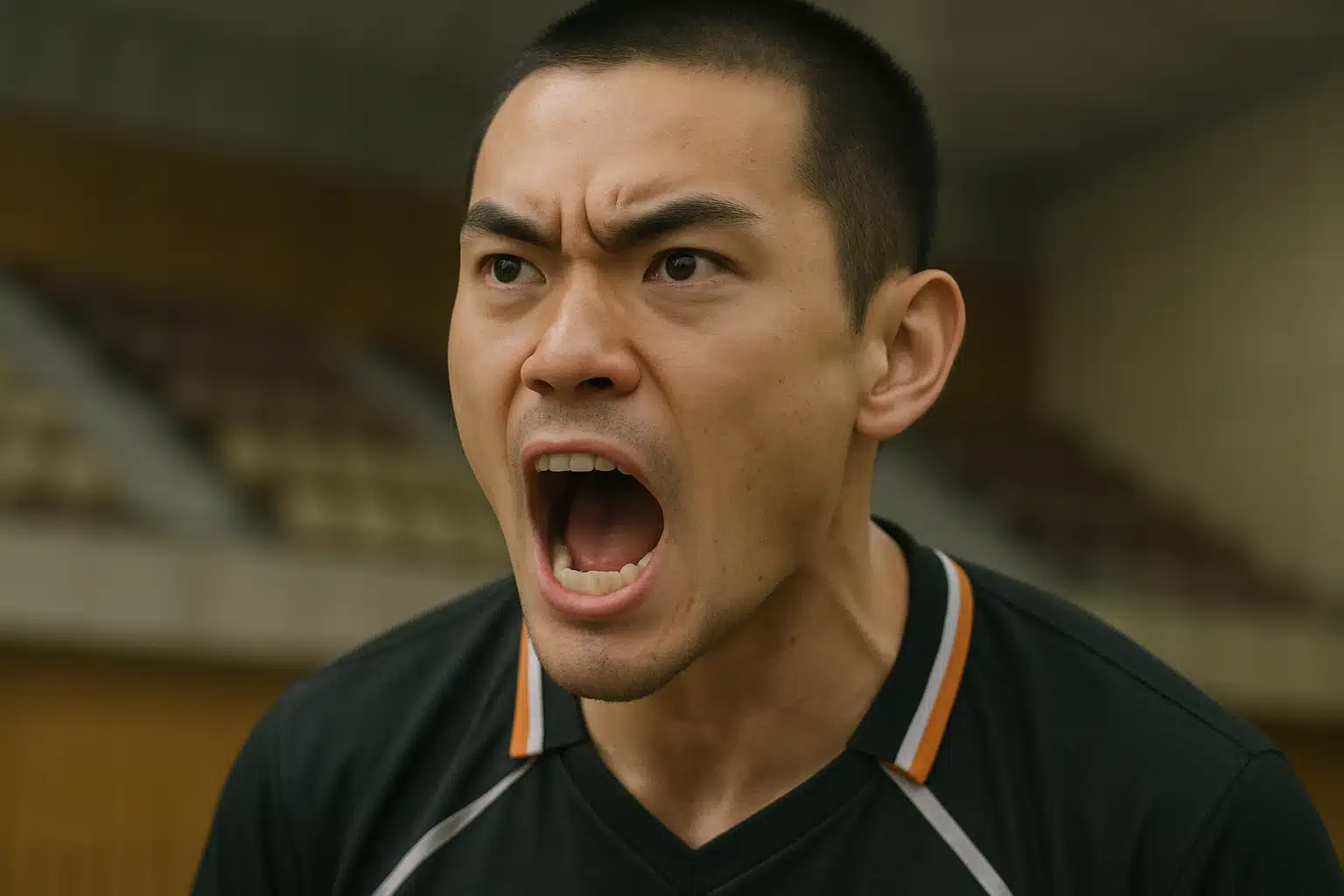あの話題作『こういうのがいい』が、なぜ「気持ち悪い」と感じられてしまうのか、ご存知ですか?
自由で軽やかな関係を描いたはずのこの作品が、特に20〜30代女性読者の間で強い違和感や不快感を呼んでいる理由とは何なのでしょうか。
本記事では、「フリーダムフレンド」という新たな関係性の提案や、登場キャラクター・ユカの描写、そして男性目線の恋愛観に対する違和感まで、丁寧に読み解いていきます。
SNSでの読者のリアルな声や、実写ドラマ化によって強まった反発、さらには作者・双龍氏の意図とのギャップまで、幅広い視点から考察しました。
読み進めることで、「なぜ自分はこの作品にモヤモヤしたのか?」という疑問に、きっと答えが見えてくるはずです。
“なんか合わない…”と感じたあの感覚、ここで一緒に言語化してみませんか?
こういうのがいい 気持ち悪いと感じる理由とは?
「こういうのがいい 気持ち悪いと感じる理由とは?」について詳しく解説していきます。
「フリーダムフレンド」という関係の曖昧さ
「フリーダムフレンド(以下フリフレ)」とは、恋愛の枠組みにとらわれず、自由で気楽な関係性を指す造語です。
セフレとも恋人とも違う独特の関係性として描かれていますが、この設定自体に多くの読者が違和感を覚えています。
「自由」を謳いながら、実際には感情的な責任を回避した関係に見えるため、「誠実さが感じられない」「感情が空っぽ」と受け取られるケースも少なくありません。
また、そうした関係が理想として肯定的に描かれていることに対して、現実味がなく無責任に感じるという声が多く上がっています。
恋愛を表層的に扱っているように見える点が、女性読者の共感を遠ざけている要因のひとつと言えるでしょう。
筆者としても、「自由」と「曖昧」は違うよなあ…とモヤモヤしますね。
ユカのキャラ設定が女性視点とズレている
ユカのキャラクターは、元気で奔放、下ネタもポンポン飛ばす「自由な女性」として描かれています。
しかし、その表現が「非現実的で下品」「同性でも友達にしたくない」と強い拒否反応を引き起こしているのです。
「おっさんのような口調」「痴女っぽい行動」といった批判は、彼女のキャラ造形が作為的に見え、リアルな女性像からかけ離れていると感じる女性読者が多い証拠でしょう。
こうした人工的なキャラクターは、自由さではなく「都合の良さ」に見えてしまうのが問題です。
「キャラが浮いてる」というより、「現実に存在しなさすぎて怖い」と感じる人がいるのも納得ですね。
男性目線の願望が透けて見える描写
作品全体が「男の理想」を全面に出したような展開で構成されているという指摘は非常に多く見られます。
たとえば、「後腐れなくセックスできる巨乳美女」「下ネタが好きで趣味が合う」という要素が重なることで、まるで都合の良い女性像をテンプレのように並べた印象を受けるのです。
このような設定が「男性読者の願望をそのまま具現化している」と見なされると、女性読者は疎外感や嫌悪感を覚えるのも無理はありません。
しかもその願望が作品の「正しさ」として提示されていることが、「押し付けられている感」になってしまうのです。
こういうの、ホントに「理想」なんですかね?ちょっと考えさせられます。
下ネタとオタク用語の過剰な使い方
「下ネタを言える女の子」は一部の男性にとって理想のキャラ設定かもしれませんが、現実の会話ではかなり特殊です。
作品内では頻繁に性的なジョークやネットスラングが使われ、キャラクターのリアリティを薄めています。
女性読者の中には、「これは共感できない」「読んでいて恥ずかしい」といった、いわゆる“共感性羞恥”を感じる人も多くいます。
特にデート中に突然上半身を見せるシーンなど、「サービスカット」の域を越えた過剰演出が見受けられ、読者を物語から遠ざける結果になっています。
筆者も「ここ笑うとこ…じゃないよね?」と困惑しました。
リアリティの欠如が共感を阻む要因に
物語全体を通して、「本当にこんな関係あるの?」という疑問がつきまといます。
キャラ同士のやりとりもどこか嘘っぽく、会話はテンプレ的で感情の奥行きが感じられません。
これにより、読者はキャラクターの行動に感情移入できず、結果的に「見ているのがつらい」「疲れる」といった感情を抱いてしまうのです。
リアルさがないからこそ、描かれる恋愛や感情のやりとりが心に響かず、「気持ち悪い」という印象に直結するのです。
筆者も「虚構って分かってても、なんか痛い…」と感じてしまいました。
女性読者の感情に寄り添わない展開
読者の多くが抱える恋愛観のリアルや悩みに対して、この作品はあまりに一方的です。
感情の描写が浅く、特に女性側の視点がほとんど描かれていないため、「自分の気持ちにまったく触れられていない」と感じる読者が多くいます。
これは、恋愛漫画に対する読者の期待—心の機微やすれ違い、葛藤など—を大きく裏切る構成とも言えます。
共感や理解がない物語に、感動や満足感を得るのは難しいですよね。
筆者自身、「なんでこの人たち、こんなに他人事みたいなんだろう」と思ってしまいました。
「気持ち悪い」という感情の正体とは?
結局のところ、「気持ち悪い」という感情は単純な嫌悪ではありません。
その背景には、現実との乖離、不均衡なジェンダー構造、表層的な感情描写、そして読者自身の経験とのギャップが複雑に絡み合っています。
SNSなどで共有されるモヤモヤ感の正体は、そうした多層的な違和感の集合体です。
「なんか嫌だな」と思ったその直感は、作品が提示する恋愛観や人間関係に対する、読者の繊細なセンサーが働いている証拠なのです。
それにしても、「気持ち悪い」って、奥深い感情なんですね〜。
SNSでの評判と読者層の評価を探る
「SNSでの評判と読者層の評価を探る」について分析していきます。
Twitter・レビューサイトでのリアルな声
SNS上では、「こういうのがいい」に対する意見が非常に活発に飛び交っています。
特にX(旧Twitter)では、「あの漫画、正直無理だった」「気持ち悪いっていうか、生理的に合わない」という投稿が多く見受けられました。
一方で、「なんか分かる」「軽い関係ってこういうのが理想かも」という肯定的な声もあり、意見は真っ二つに分かれています。
めちゃコミックや読書メーターなどのレビューサイトでは、星1~2の低評価レビューの中に「疲れる」「共感できない」「キャラが現実離れしている」というキーワードが頻出しています。
その一方で、高評価レビューでは「自由な関係ってありだと思う」「笑えるし楽しい」といったライト層の支持も確認できました。
「合う人には合う、合わない人にはとことん合わない」—そんな割り切れないズレが見えるのがこの作品の特徴ですね。
好意的な意見とのコントラスト
面白いのは、肯定派の意見にもどこか“限定的”なニュアンスがあることです。
「こういうのも“フィクションとして”ならあり」「現実では無理だけど、漫画なら読める」といった、「距離感を保った楽しみ方」が多く見受けられます。
また、「日常に疲れてるときに読むとちょっと癒される」という声もあり、むしろ“深く考えないで読むもの”として支持されている印象があります。
一方で、否定的な意見はより感情的かつ批判的で、「このキャラをリアルに置き換えると寒気がする」「ドラマ化したらマジで見てられない」というような、強い拒否反応が特徴的です。
このギャップは、読者が作品を「現実的な人間ドラマ」として求めるか、「非日常の娯楽」として消費するかの姿勢の違いから来ていると考えられます。
うーん、読む側のスタンスで評価が激変する作品って、やっぱり興味深いですよね。
ドラマ化による印象の変化
2024年の実写ドラマ化は、作品への反応にさらに揺さぶりをかけました。
特にSNS上では、「漫画では許せたけど、実写だとマジでキツイ」といった感想が目立ちます。
ユカ役の女優が演じるリアルな振る舞いが、原作以上に「うざい」「現実にいたら絶対嫌」と感じさせるようです。
また、「演技がベタすぎる」「キャラの可愛げがなくなった」といった意見もあり、原作の抽象的な魅力が失われたと感じる人が多いことが伺えます。
中には「ドラマ観てから原作読み返したら、前より気にならなくなった」という逆パターンもあり、実写化が作品の受け止め方を変える要素になっているのは間違いありません。
筆者としては、実写になるとどうしても“現実っぽさ”が強調されてしまって、フィクションの中の軽やかさが失われる気がするんですよね。
読者層別の受け止め方の違い
この作品に対する反応は、読者の性別や年齢、そして恋愛観によって大きく分かれます。
20代~30代の女性読者、特に恋愛にリアルな感情のやり取りを求める層からは、拒否感を持たれる傾向が強いようです。
一方、男性読者やライトな読み物として捉えている層、あるいは「関係性の実験」として興味を持つ層には、むしろ面白く感じられているようです。
また、「恋愛に疲れた経験がある女性」からは、「理想とは思わないけど理解はできる」という意見も。
つまりこの作品は、「どんな恋愛をしてきたか」「今どんな関係を望んでいるか」が反応に直結するタイプのものなんですね。
そういう意味では、「恋愛観の鏡」みたいな作品かもしれません。
「セフレ」との境界線にある違和感
「フリフレ」と「セフレ」は一見似ているようで、微妙な違いがあります。
本作では「付き合っていないけど特別な関係」「お互いを尊重している」など、単なるセフレとは違うニュアンスが加えられています。
しかし読者からは、「ただのセフレを美化してるだけ」「結局は都合のいい関係じゃん」という冷めた声も目立ちます。
特に女性からは、「本当にそんなに都合よく感情を切り分けられるの?」という疑問が多く、そこに“気持ち悪さ”を感じてしまうのです。
「セフレよりセフレしてる」といった皮肉めいた感想も散見され、ネーミングの工夫だけで本質を隠せていないのでは?と感じる読者もいるようです。
うん、「名前だけ変えても中身が変わらない」ってこと、よくありますよね…。
恋愛観に対する価値観の衝突
本作が提示する「恋愛の自由」「縛られない関係性」という価値観そのものに、賛否が集まっています。
「縛られたくない人間関係もある」という声に対して、「関係には信頼や責任が必要」という声が真っ向からぶつかるのです。
一部読者にとっては、この作品がまるで「感情的な責任を放棄した恋愛の理想化」に映り、「それって恋愛じゃなくて逃げでは?」という疑問を呼んでいるのです。
現代の多様な恋愛観を描こうとした点は評価できるものの、その提示の仕方が“男性視点に偏りすぎている”と感じられると、一気に冷めてしまうようです。
時代が変わっても、「対等さ」って、やっぱり恋愛の基本なんだなと感じさせられます。
作品が引き起こした文化的議論とは?
『こういうのがいい』は、単なる恋愛漫画ではなく、現代の恋愛観、ジェンダー観、そしてフィクション表現に関する議論を巻き起こした作品でもあります。
「自由な恋愛とは?」「男女の対等性とは?」「フィクションにおけるリアリティとは?」といったテーマが、読者間で議論されるきっかけとなっています。
ある意味、この「気持ち悪さ」は、読者それぞれが自分の価値観を改めて見直すきっかけにもなっているのかもしれません。
好意的な意見も批判的な声も、この作品に対する関心の深さの裏返しです。
違和感があるからこそ語られ、語られるからこそ意味が生まれる。
筆者としては、こういう作品が存在すること自体が、むしろ健全なことだと感じますね。
作者の意図と現実とのギャップを読み解く
「作者の意図と現実とのギャップを読み解く」について掘り下げていきます。
作者・双龍氏のインタビューから見える方向性
作者・双龍氏は、インタビューの中で本作について「自由で軽やかな男女関係の日常を描きたかった」と述べています。
また、「登場人物がどこで出会ったのかは考えていなかった」「次に何が起きるかを決めて描いているわけではない」とも語っており、即興的かつキャラクター主導のスタイルが基本であることが分かります。
このような姿勢から、物語におけるリアルな恋愛模様というよりも、「空気感」や「なんとなくいい感じ」を重視した構成であることがうかがえます。
つまり、「緻密な設定」や「キャラのバックボーンよりも雰囲気」を優先した作風なんですね。
その軽やかさが魅力にもなりますが、同時に「物語としての深みの欠如」と感じられる側面もあるようです。
うーん、悪く言えば“ふわふわした印象”なのかも…。
「軽やかさ」と「不快感」が生まれる理由
双龍氏が意図する「軽やかさ」は、従来の恋愛漫画にありがちな「重さ」や「しがらみ」から解放された関係性として、理想的に描かれているようです。
しかし、これが一部読者には「軽すぎて空虚」「責任や感情のない関係を理想として押し付けられているよう」と捉えられてしまう。
特に“恋愛は感情のキャッチボール”と考える読者にとっては、「誰も何も背負わない関係」がリアルに感じられず、かえって不気味に映るのです。
これは、恋愛を「軽く描く」ことで、現実にある“重さ”や“痛み”を無視しているように感じさせる、というギャップでもあります。
「軽やか=無責任」に見えてしまうと、そこに不快感が生まれるのも納得ですね。
キャラ造形の即興性が与える印象
「キャラクターが勝手に動いてくれる」という作り方は、自然でリアルな物語を生む可能性がある一方で、「作者の意図が感じられない」「軸がない」とも受け取られかねません。
実際にユカの行動やセリフが「不自然」「場にそぐわない」と感じられる場面では、即興的な演出が裏目に出てしまっているように見受けられます。
特に読者がキャラの背景や動機を知りたがるタイプだと、根拠がないキャラ設定には感情移入が難しくなる傾向があります。
その結果、「このキャラは本当に存在するように思えない」という“構築物感”が拭えず、共感どころか拒否感を抱いてしまうんですね。
筆者的には、「描く側の自由」と「読む側の納得」って、やっぱり両立しないと厳しいんだなぁ…と実感しました。
意図しないファンタジー化の危うさ
双龍氏は「特定のメッセージを押し付けるつもりはない」と語っていますが、その“無意識性”がむしろ危険な方向に働いてしまう場合もあります。
たとえば、作者の無自覚な偏りが、キャラクターや物語全体を“男性の願望”として読ませてしまうのです。
ユカという存在が、あまりに理想化された「都合のいい女」として機能してしまっているとき、そこには意図せぬファンタジーの力が働いています。
それが「現実の女性像」と大きく乖離しているため、読者は「なんだか気持ち悪い」と直感的に感じてしまうのです。
“押し付けてない”つもりが“自然に見せかけた押し付け”になってしまっているパターン、意外と多いんですよね。
感情の複雑さを描ききれていない問題
恋愛や人間関係には、常に“矛盾”や“曖昧さ”がつきものです。
ところが本作では、感情の揺れや複雑さがほとんど描かれず、どこか一直線で“整いすぎた”関係が展開されていきます。
特にユカは、「気楽で下ネタ好きな明るい子」というテンプレ的なキャラで留まっており、その内面や矛盾がほとんど掘り下げられていません。
そのため読者からは「感情が浅い」「人間じゃなくてキャラに見える」といった声が多く寄せられています。
物語において“感情の揺らぎ”こそが共感の種になるので、それが欠けていると、どれだけ設定が面白くても心に残らないのです。
筆者としては、「ちゃんと心が動いてる瞬間」を見せてほしいな〜と思ってしまいますね。
男女観・恋愛観の表現にある偏り
作品を通して浮かび上がるのは、「男性が都合よく感じる関係性」の理想像です。
女性が何も求めず、癒やしを与えてくれる存在として描かれているユカは、あくまで“受け手”の役割に甘んじており、自ら何かを求めたり、葛藤したりすることがほとんどありません。
また、男性キャラである村田の視点が常に中心に置かれ、「ユカにとってのこの関係の意味」は語られないままです。
こうした構成は、「女性の主体性が描かれていない」と受け取られ、ジェンダー的にバランスを欠いているという批判を招いています。
恋愛の“相互性”を大切にしたい読者にとっては、これは致命的な構造かもしれません。
やっぱり「対等な視点」って、恋愛描写の基本ですよね…。
「こういうのがいい」という表現の功罪
本作のタイトルでもある「こういうのがいい」という言葉には、作品全体の価値観が集約されています。
ただし、それが“あまりに断定的”に響いてしまうため、「いや、全然よくないよ…」という反発を生んでいるのも事実です。
人によって理想の関係は違うはずなのに、「こういうのが正解」みたいな押し付けがましさを感じさせるのです。
特に、“理想像が男性目線に偏っている”と感じられる場合、そのタイトル自体が「価値観の違い」を煽るトリガーになってしまいます。
言葉はシンプルですが、だからこそ強く刺さってしまう。読者の反応を見ていると、タイトルの「功」と「罪」の両面を感じずにはいられません。
筆者としても、「こういうのがいい、って誰にとって?」という問いが頭を離れませんでした。
まとめ
『こういうのがいい』は、自由で軽やかな恋愛関係をテーマにした話題作です。
しかし、多くの女性読者からは「気持ち悪い」と感じられ、その理由がSNSやレビューで広く議論されています。
主な要因としては、男性視点の願望が強く反映されたキャラ描写、感情の浅さ、ユカの不自然な言動、そして「フリーダムフレンド」という関係性のリアリティ不足などが挙げられます。
さらに、実写ドラマ化によってそれらの問題がより明確に浮き彫りとなり、好意的だった読者からも「やっぱり違和感がある」といった声が上がりました。
作者の意図と読者の受け止め方のズレも、作品の評価が二極化する一因と言えるでしょう。
この作品は、恋愛観やジェンダー観が揺れる現代において、一石を投じる存在であることは間違いありません。
今後もSNSなどを通じて、感想や議論が広がっていくことでしょう。